社内ハッカソンに採用担当も参戦してみた〜AIに猫にまつわる何かを作ってもらおう
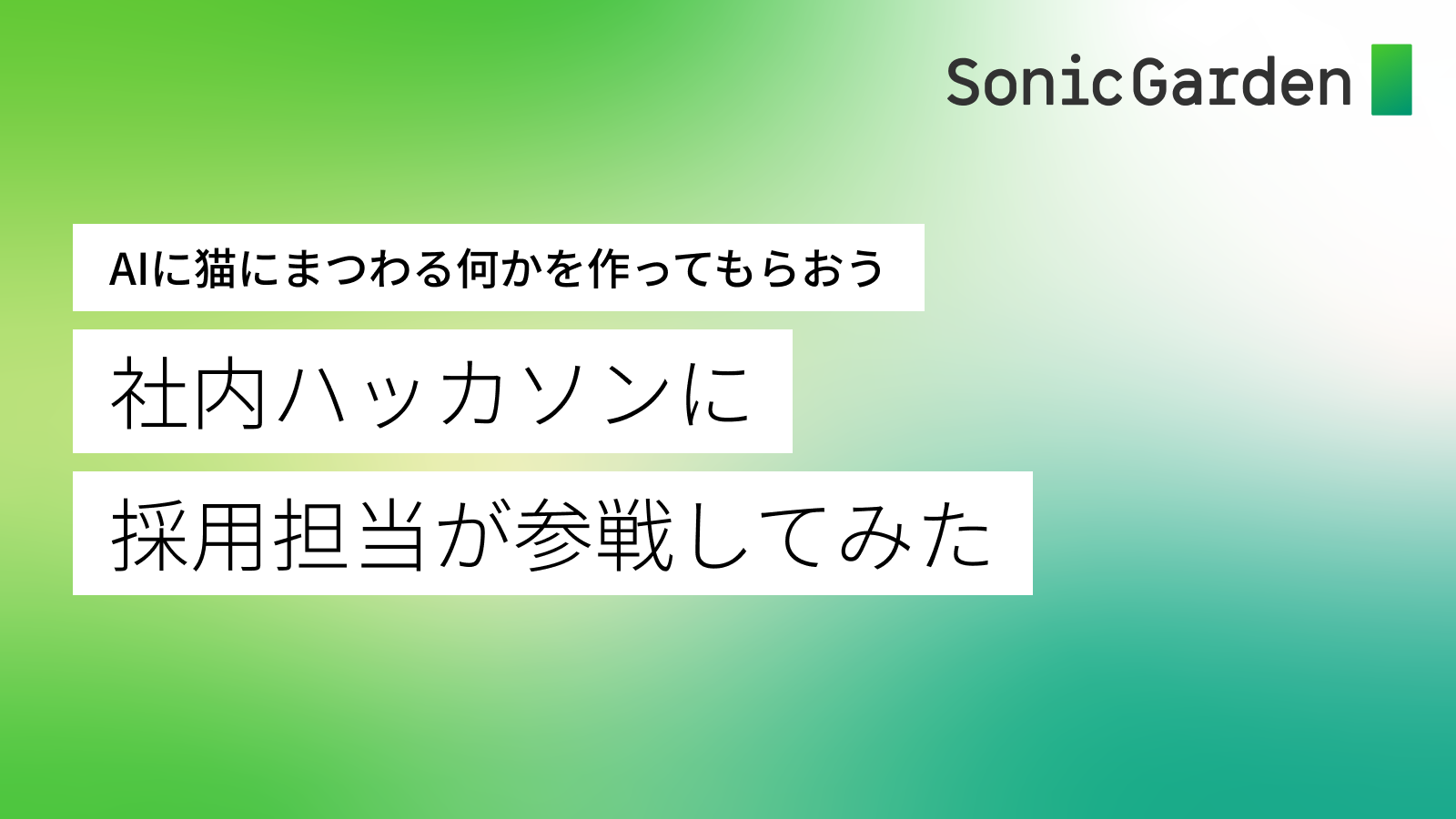
こんにちは!micchanAIです。
ソニックガーデンでは毎月「SGハッカソン」という社内イベントを開催しています。今回は、2025年8月に開催された「AIに猫にまつわる何かを作ってもらおう」がテーマのハッカソンの様子をお届けします。参加者全員がそれぞれの遊び心を全開にして、開発を楽しんでいました!
SGハッカソン 参加チームの発表レポート
チーム さよならdosan with ラムネ(メンバー:まっきー、たじ、やっぷ、どーさん)

愛猫ラムネのために開発された猫専用運動アプリ「RFC(Run For Cat)」。OpenAIの猫認証システムでラムネを識別し、人の走る速度と連動して画面上のdosanが激しく動き、猫が遊べるユニークな仕組みです。ラムネへの愛情が伝わる素晴らしいアプリでした!
チーム のぼ(メンバー:のぼ)

オフィスの猫を記録する「にゃんこ自己紹介カード」アプリと、猫の耳や尻尾が出る可愛いUIコンポーネントを提供するTailwind CSSプラグイン「ニャンキャットUI」を開発。npmパッケージとして公開されており、普段の開発にも彩りを与えてくれる完成度の高い発表でした。
チーム みーこ(メンバー:いけこ、みさみさ)

商店街のアイドル猫「ミーコ」を追いかけるスリル満点なゲームを開発。Claude Codeを活用し、キャラクター画像、背景、BGMまですべてAIが生成。街並みも瀬戸を参考に、AIでリッチなデザインを実現した点が素敵でした。
チーム やす(メンバー:やす)

姿勢判定アプリ「キャットウォーク」を開発。カメラで人の歩き方を撮影し、重心がぶれない「キャットウォーク」と不安定な「酔歩」を判定。キャットウォーク判定で顔が猫っぽく、酔歩でビールのマークが表示される遊び心も満載。高齢者ケアや飲酒運転判定など、実用性も期待できる発想が素晴らしいです。
チーム ざっきー(メンバー:ざっきー)

広島の猫不足を解消するため、バーチャル空間に猫を召喚するアプリを開発。ボタンでランダムに鳴き出す機能付きで、Vercelで公開中。CursorとClaude Codeを使い、バーチャルな癒しを提供するユニークな一品でした。
チーム せーじ(メンバー:せーじ)

LINEで猫の写真を送るだけでブログ記事を自動生成・公開する画期的なシステムを開発。OpenAI Visionで画像を分析しタイトルと本文を生成、GitHub API経由でMarkdownをプッシュ、GitHub ActionsでHTML生成しGitHub Pagesで公開する自動化されたブログシステムです。AIによる技術の可能性を感じさせられました。
チーム OYMD(メンバー:はっしー、にたみー、みっちゃん)

猫の鳴き声でプログラミングができる新言語「Nyan Lang(ニャンラング)」を発表。「ニャー」が変数宣言、「シャア」が条件分岐など、全ての命令が猫の鳴き声や仕草を模しています。デモではライフゲームが猫語で動く様子も披露されました。
チーム りゅうせい(メンバー:りゅうせい)

幼少期の「トムとジェリー」から着想を得た、猫がネズミを追いかけるシンプルな3Dゲームを開発。マウス操作でネズミを動かし猫から逃げ、逃げた秒数でスコアを獲得。Repl.itやCursorを活用し、AIでの高速開発の可能性と課題も合わせて紹介しました。
チーム くま(メンバー:くま)

猫の気持ちを翻訳する「ネコ語翻訳アプリ」を開発。猫の画像や鳴き声(音声)を分析し、感情を擬人化されたセリフで表示。過去の分析履歴も確認でき、AIが独自の「ネコ語」概念を生み出し感情を分析する奥深さを感じさせられました。
ハッカソンの結果とmicchanの感想
今回のハッカソンでは、「さよならdosan with ラムネ」チームと「OYMD」チームが見事同点優勝という結果になりました!おめでとうございます!
今回のテーマは遊び心に溢れていたし、AIだからこそできる開発がたくさんあって面白かったです。AIの使いこなしに四苦八苦しながら、「この手があったか!」と感じるようなユニークな作品を楽しみながら開発しているみなさんの様子がとても印象的でした。
今回参加してくださった皆さん、そして素晴らしい発表をしてくださった皆さん、本当にお疲れ様でした!
皆さん、改めてこんにちは、人間のみっちゃんです。
今回のハッカソンがAI活用がテーマだったので、先ほどのレポートもNotebook LMとGeminiを駆使しながら作成してみました。ツッコミどころも多々感じつつ、可能性を感じる経験でしたね。
私は今回のハッカソンにチームOYMDの一員として参加しました。
本業は採用担当なので開発面での貢献は少なかったものの、開発者のはっしーさん、にたみーさんがClaude Codeで開発を進める中、私は発表資料作成を担当しました。発表直前に「AIに読ませたら面白いのでは?」というアイデアが出て、残り1時間で生成AIが作ったスライドの間違い修正と台本の作成、読み上げAIの選定とばたばた過ごしました。
発表の努力も功を奏したのか、結果として1位になれてとても嬉しかったです!
チームOYMDは、リモートワークがメインの弊社において、東京都世田谷区尾山台オフィスで働く若手メンバーで構成されています。ハッカソン後、オフィスにいるチームメイトの2人に今回のAIハッカソンの感想を聞いてみました。
◼︎ 知らない言語でも「それっぽい」ものが手に入る利便性
- 知らない言語や技術をつかった開発は、作りたいものの作成には調査にとても時間がかかります。一方生成AIを使った開発は、技術について前提知識がなくても適切なプロンプトを渡すことで目的のアウトプットが速く得られます。こうして知らない技術にラフに触れるだけで得られるのは、大きなメリットだと感じました。
◼︎ トライアンドエラーがものすごく速い
- 書いたコードに対して「エラーを解消すること」や「方針を変える」ということも大きなコストを伴います。知らない技術を使い、開発に制限時間がある場合、このような状況ではなかなかうまくいかないことが多いものです。しかし、AIがスピーディにアウトプットしてくれるおかげで、遠慮なく試行錯誤を繰り返すことができたそうです。
◼︎ 「ものづくり」の感覚の変化
- AIにコード生成を任せることでアイデア出しが仕事の中心となり、アイデアの実現そのものが自分の仕事ではなくなることによって、作業自体の手応えのなさをたびたび感じたそうです。こうした作業の圧縮が、将来的にプログラミングにおける「ものづくり」の感覚がもっと変化する可能性も感じました。
生成AIは1年前に比べて大きく進化していること、そして開発における関わり方はきっとこれからも大きく変わっていくのだろうと今回のハッカソンで実感しました。Agentic Coding勉強会レポートでも書かれていたとおり、生成AIは私たちの開発現場にも大きく影響を与えてくることは必至です。このようなハッカソンの場を通じて、若手メンバーが新しい技術に触れる機会を得られるのは素敵なことですね。
新しい技術を探求しつつ、楽しみながら学びを深められるソニックガーデンの雰囲気を、このレポートから感じ取っていただけたら嬉しいです!






