「納品のない受託開発」に興味を持っていただき、ありがとうございます。
「お客さまに無駄遣いして欲しくない」「本当に価値ある機能を作りたい」「開発に関わる人すべてを幸せにしたい」・・・そう考えて新しいビジネスモデルを生み出しました。
月額定額で顧問のように寄り添い、事業の相談に乗るところから関与し、システムの設計・開発・運用、さらにエンジニアチームのマネジメントまで、ワンストップで担います。
納品して終わりの関係ではなく、お客さまの一員として事業成長に貢献し続けます。システム開発の頼れるパートナーをお望みなら、私たちソニックガーデンにお任せください。
開発で起きる問題
ソニックガーデンの受託開発では、一括請負を行っていません。システム開発における「一括請負の納品型での受託開発」は、以下のような問題を抱えているからです。
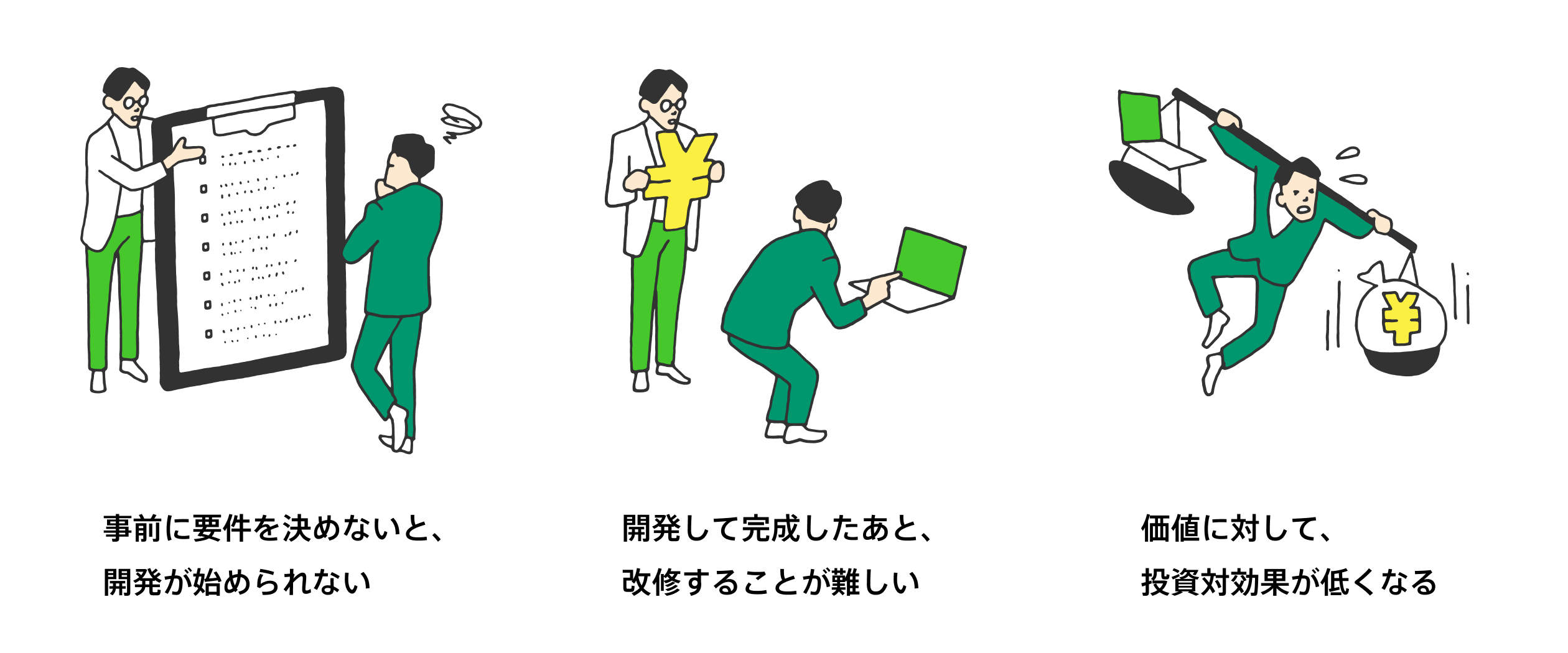
1.事前に要件を決めないと、開発が始められない
一括請負では、最終的に納品するために、作るべき機能を最初に決める必要があります。それを要件定義と呼びます。しかし、事前に予見することは非常に難しく、たとえ要件定義した通りに完成しても、想定通り使えるものになるかは未知数です。
市場環境や社内の状況、利用者のニーズなど世界は変化し続けています。そんな中で、要件を事前に決めないといけないことは大きなリスクになりえます。
2.開発して完成したあと、改修することが難しい
一括請負では、システムを納品してプロジェクトは終了となります。その後で、実際に使い始めてから修正したい箇所が出てきたら、また見積もりから始まります。チームは刷新されてしまうため、ちょっとした改修でもコストが高くなりがちです。
完成後の改修費用は事前に把握できず、たとえ高額になっても受け入れざるを得ません。このことはシステム開発を発注する際の大きなリスクと言えます。
3.価値に対して、投資対効果が低くなってしまう
一括請負では、労働集約で見積もりを行うため、個々人の生産性を上げることよりも、下請けを使うなどして多くの人員を投入する方向にインセンティブが働きます。しかし、人が増えると本来は必要ではなかったコストが発生することになります。
また、機能・納期・品質を固定した状態で納品を目指すと、受注する開発側は多くのリスクバッファを積まざるを得なくなり、投資対効果が低くなります。
あるべき開発の姿
一括請負の受託開発が抱える問題の本質は、納品が発注側にとってのスタートに対して、開発側にはゴールだという点です。本来の目指す開発は、以下のような姿です。
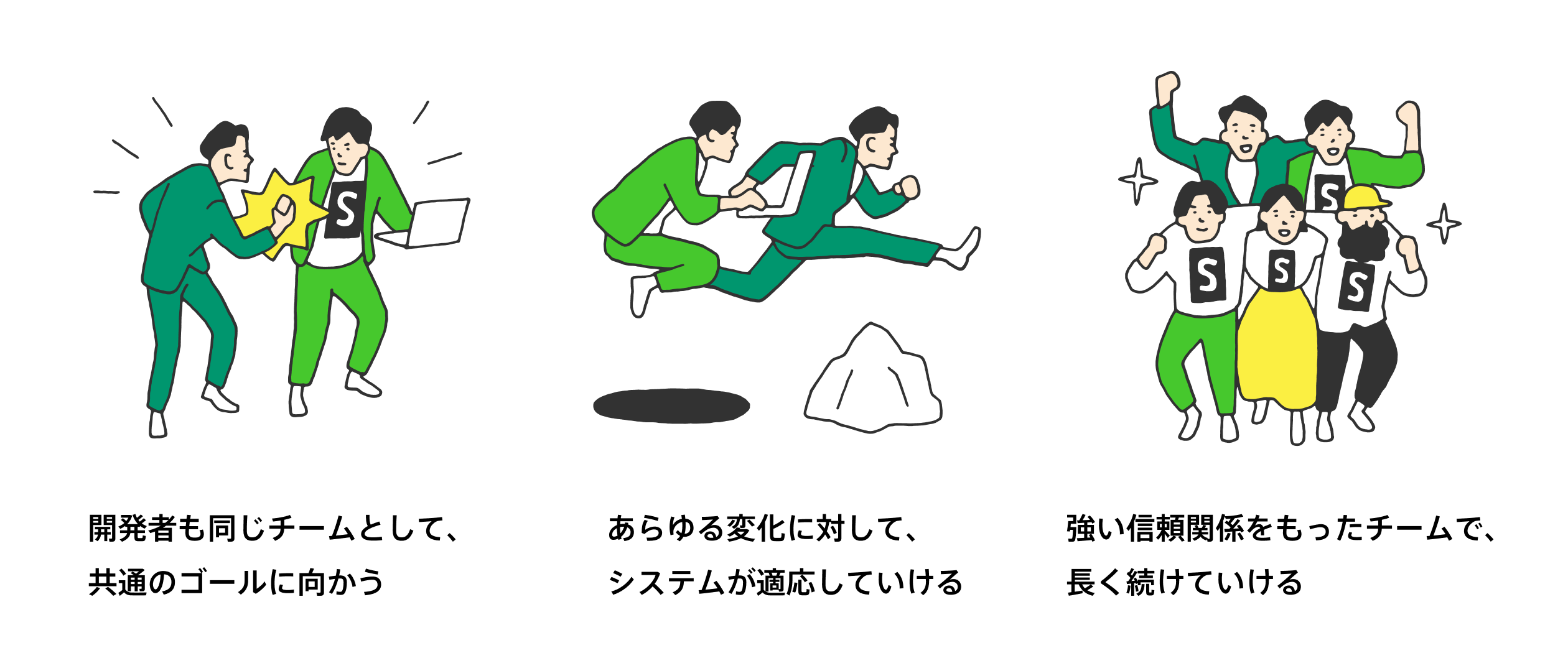
1.開発者も同じチームとして、共通のゴールに向かう
事業側と開発側が同じチームになれば、開発者は言われたものだけを作るのではなく、達成したいゴールのために積極的な提案ができるようになります。そもそも、どういったシステムを作れば良いか、開発する前から相談しあうことができます。
新規事業にせよDXにせよ、今はシステムを前提としないビジネスはありません。そのため事業を推進するプロと、システムを開発するプロが同じチームでいることは理想です。
2.あらゆる変化に対して、システムが適応していける
システムは作って終わりではなく、より便利で効率的に、使いやすく改善していくことで事業は成長していきます。逆に、事業の成長にあわせて、システムも拡張していく必要があります。そうした変化に柔軟に適応し続けられる状態が理想です。
また、最初は小さく始めることも正解のないプロジェクトでは重要です。小さく試して、得られた学びをシステムに取り込んでいくためにも、変化に適応する力は求められます。
3.強い信頼関係をもったチームで、長く続けていける
プロジェクトごとに解散するチームではなく、扱うシステムに詳しいチームが持続的に維持されていることで、業務知識にも詳しくなり、より最適な提案につながります。メンバーの成長が成果に直結するため、互いの成長を喜ぶ文化ができます。
関係が長く続けば事業側を含んだチームでの信頼関係も深まり、心理的安全性の高い状態を作ることができます。強いチームワークによって大きなパフォーマンスを発揮します。
私たちの提供価値
一括請負の受託開発では対立構造に陥りがちなため、解決策として期待されているのが内製の開発チームです。しかし、内製のシステム開発には以下の困難が伴います。
- 採用:エンジニアの人材獲得は熾烈な状況
- 育成:エンジニアの育成には時間がかかる
- 報酬:エンジニアの報酬は他職種より高い
- 定着:エンジニアの人材流動性は特に高い
- 運用:安定した運用には高度な人材が必要
ITが専業ではない事業会社にとって、上記のようなエンジニアのマネジメントは非常に難しいものです。まして、エンジニアの組織を作るとなれば、評価や制度など経営者や事業責任者には相当な知見と経験が求められます。
納品をなくせば、うまくいく
そこで私たちは、あるべき開発の姿を受託開発でも実現するために「納品」をなくすことを考えました。
納品がなくなれば、要件定義も労働集約の見積もりも不要となり、業務とシステムをよく理解したチームが維持できることで継続的な改修も容易になり、リスク対策のための余計なバッファも減って、少数精鋭で生産性の高い開発と安定した運用を実現できます。
なにより納品をなくせば、お客さまと私たち開発側が一つのチームになることができます。さらに内製の開発チームに比べて、以下のような良さがあります。
- 徹底的に選抜された優れたエンジニアが在籍している
- エンジニア同士の連携で、あらゆる課題に対応できる
- 雇用と違うため、労務管理や人事評価をしなくてよい
- 持続的な体制を維持し、人の増減も柔軟に対応できる
- 最初から高セキュリティで安定のクラウド基盤がある
経営者や事業責任者と共に、どうすれば事業が成長するか考えて、成長を実現するためのシステム開発と改善を行い、セキュリティも堅牢で安定したシステム運用を実現し、さらには事業拡大にあわせてエンジニアチームの立ち上げからマネジメントまでを行います。
それが、私たちの提供する「納品のない受託開発」です。
お客さまへの約束
一緒に悩んで、いいものつくる。
「納品のない受託開発」の根底にあるのは「お客さまと共にいいものをつくりたい」という思いです。
私たちが考える「いいもの」とは、確かな事業成長につながるもの。そして、変化に適応し続けられるものです。そのために私たちは、納品して終わりという関係を超えて、お客さまの本物のパートナーとして、継続的に伴走します。
抱える課題に対して深く理解し、本当に必要な機能や優先順位を見極めていく。時には共に悩みながら適切な解を導きだし、機動性高く開発と改善を繰り返す。その積み重ねによって、お客さまの事業に合わせて成長し続けるソフトウェアを具現化していきます。

