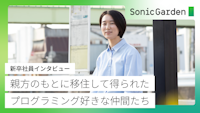視点を増やせば、もっと組織は楽しくなる!〜 「こだわらない」育成者が考える成長戦略

今回登場するのは、創業メンバーの松村章弘(まつむらあきひろ)さんです。
ソニックガーデンの立ち上げから関わり、10年を駆け抜ける中で、プログラマとして、社員育成のチーフとして、ソニックガーデンという組織を育てる仕事に深く貢献してきました。
組織が成長し大きくなることは止められない。では場をより良いものに整え、より良い仕事をするために何が必要なのか?と考え続けた10年。今なお成長し変容するソニックガーデンを見つめる松村さんの、過去、現在、未来について伺いました。
目次
あっという間「じゃない」10年
⎯
では、お名前からお願いします。
 松村
松村ソニックガーデンCTO(顧問プログラマ)松村章弘です。
⎯
松村さんは創業メンバーなんですよね。創業から10年経ちました。
 松村
松村そうですね、もう10年。でもあっという間な感じはしないかな。いろいろあったな、とは思いますけど。
⎯
長く何かを続けてると、「あっという間だったでしょ?」ってよく言われますけど、まだソニックガーデンの歴史の真っ只中にいるんですもんね。
 松村
松村終わってたら「あっという間だったな」って言えるかもしれないけど、別に終わってないし、今もずっと悩みは尽きないし…。
⎯
新たに、どんどん出てきますよね、悩みは。
 松村
松村本当にいろいろ、ひっきりなしに出てきます。ソニックガーデン自体が、あるひとつの形に固まって、ずっとそれでいこうということは一切しないので。
⎯
存続するためには変化と成長は避けられないですし、特にそういうアイディアが豊富なところもソニックガーデンの特徴であり、良いところでもありますよね。
人の人生を変えてしまう仕事
⎯
そんなあっという間「じゃない」10年、今は主に育成の部分を担当していると伺いました。どのようなお仕事ですか?
 松村
松村採用から、独り立ちして「納品のない受託開発」に取り組めるようになるところまでですね。
⎯
採用から関わってるんですか。
 松村
松村そうです。最近は育成自体にチームを作って取り組むようになったので分担し始めたところなんですが、基本的には、最初に申し込んで面談をするところから。今活躍しているメンバーは、僕が面談から関わった人ばかりですね。
⎯
ソニックガーデンは採用にかなり時間をかけるんですよね?
 松村
松村最大で1年かそれ以上かけます。
ソニックガーデンとして求めている人材かはもちろん、ソニックガーデンの考え方にフィットする人物か、あとは応募してきた方自身が、本当にソニックガーデンでいいのかとか、いろんな目線から合っているかを考えて話し続ける、みたいな感じで。
ソニックガーデンとして求めている人材かはもちろん、ソニックガーデンの考え方にフィットする人物か、あとは応募してきた方自身が、本当にソニックガーデンでいいのかとか、いろんな目線から合っているかを考えて話し続ける、みたいな感じで。

⎯
ずっと、何度も面談するんですか?
 松村
松村面談もしますが、それだけじゃなくて、その採用の過程で技術を学んでもらったり、ソニックガーデンへの理解を深めてもらったり、とにかくずっとコミュニケーションを取り続けます。その上で、お互いに認識が揃ったら、さらに今度はソニックガーデンの中に入ってもらって、「納品のない受託開発」に携われるようになるところまで、毎週毎週ふりかえりをして、伝えていきます。
⎯
最初の選考から全部地続きになっているんですね。それだけ丁寧に人を見るとなるとかなり大変そうに見えます。一度に採用する人数は抑えているんですか?
 松村
松村そうですね、年に1人とか2人とか。ここ数年は少し許容量が増えてきていて、僕が見れる範囲で年に2、3人です。新卒は別のチームが採用するので、僕は中途採用だけ。負荷がすごくかかるかというとそんなでもないですが、考えることは多いですね。
⎯
人を選ぶのって、お互いにとって責任が重いですよね。
 松村
松村本当にそうです。最初はやりたくなかったんですよ。
⎯
(笑)
 松村
松村
だって人生がかかってるじゃないですか。ソニックガーデンに入れても入れなくても、面接に来ている目の前のその人の人生は変わる。そんな判断したくない、と思ってましたね。
⎯
人の人生に関わるの怖いですよね。
 松村
松村なるべくこっそり生きていたいなという気持ちがあるので。
⎯
なのになぜかいつの間にか前面に出るようになってしまったんですね…(笑)。
高すぎるハードルをどこまで下げるか
⎯
採用に携わるようになったきっかけはありますか?
 松村
松村創業間もない頃に、当時のメンバーと、「みんな役職名つけよう」「C(Chief)なんちゃらにしよう」ってノリで決めたんですよ、肩書きを。それでなんとなく「CTO(Chief Technology Officer)」なんですけど、そういう肩書きがついているならなにか組織のための役割を担わなきゃいけないのかな、と思って…。あとはキャラクタ的に僕が1番合ってるのかな、と。
⎯
メンバーの中で1番人当たりがいい、ということで。
 松村
松村人当たりがいいというか、他の人は「ソニックガーデンはこうあるべきだ」っていう基準がめちゃくちゃ高かったんですよね。
でも、応募の段階で思考量や知識がその高い基準に到達できている人なんていないんですよ、基本的に。
でも、応募の段階で思考量や知識がその高い基準に到達できている人なんていないんですよ、基本的に。
⎯
そうでしょうね…。
 松村
松村だから入口にその基準を置いて来る人来る人はねてたら、誰も入れない。でもソニックガーデンとしては、ありがたいことにお客さんがたくさん来ていて、なんとか仲間を増やして対応していきたい。
⎯
松村さんはその基準がもう少し柔軟だった?
 松村
松村うーん、言葉が難しいんですけど、受け入れられるというか、「まずここから始めてみようか」と思えるというか。
⎯
客観的に、引いた視点で見られるということなのかもしれないですね。基準を下げるというよりは、人の伸びる線みたいなものを見ることができるというか。
 松村
松村そうですかね。でもそれも最初はあんまりなかった気がします。
⎯
じゃあ最初の最初は大変だったんじゃないですか。
 松村
松村人を見るということ自体慣れないですし。それこそもういっぱい落としてしまって「誰もいないじゃないか」って。それで代表の倉貫さんが「この人もうちょっと見てみようよ」って言ってくれたりすることもあって、期間を長く設けて見るようになったというか。年齢のせいもあるかもしれないですけど「待てる」ようになりました。
プログラマの仕事って、作って、できあがったらお客さんに見せて、「やったね!」ってフィードバックがあって、全体のスパンが短いんですよね。そういうサイクルの早さに慣れちゃってるから、そっちの方が気持ちいいんですよね。特に若い頃は、スパンの短い仕事の方が楽しい要素が多いじゃないですか。
プログラマの仕事って、作って、できあがったらお客さんに見せて、「やったね!」ってフィードバックがあって、全体のスパンが短いんですよね。そういうサイクルの早さに慣れちゃってるから、そっちの方が気持ちいいんですよね。特に若い頃は、スパンの短い仕事の方が楽しい要素が多いじゃないですか。
⎯
結果はすぐに欲しいですよね。

 松村
松村
年を経て、いろんな経験を経て少し待てるようになったんです、多分。
⎯
ソニックガーデンの採用には「トライアウト」という仕組みが使われています。これはどなたが考えたんですか?
 松村
松村採用を始めた当初から、課題は出していたんです。でも全部手動で僕がやってた。倉貫さんが最初の本を出した時に、急に応募してくる人が増えて、「これは回らないぞ」「今後もっと増えそうだぞ」となって数人で仕組みを作りました。
トライアウトの仕組みも変遷があって、最初はやっぱりめちゃくちゃハードルが高かったんですよ。
トライアウトの仕組みも変遷があって、最初はやっぱりめちゃくちゃハードルが高かったんですよ。
⎯
ここにも壁が(笑)。
 松村
松村最初に結構な量の課題をこなさないと面談さえ行けない、という。全然誰も面談にたどり着かない。
⎯
それじゃあいつまで経っても仲間が増えませんね…。
 松村
松村そうそう。それでも応募総数が多かった頃はそこを越えてくる人もいて。今のメンバーですけどね。それで「もうちょっと受け入れようよ」って、バランス見て試行錯誤しつつ、アップデートして。
⎯
トライアウトひとつとってもそんな変遷があったんですね…。
育成において、成功も失敗も定義できない
⎯
採用にしろ育成にしろ、人を見るときに大事にしているところってありますか?
 松村
松村やっぱり文化的な部分ですね。ソニックガーデンは考え方がユニークだと思っているので、そこに共感できるかというところは最重要ポイントです。
⎯
「ソニックガーデン流」というものですね。
 松村
松村そうです。わかりやすいのはサイトにも記載されている、ソニックガーデンの企業理念と価値観。そこに共感してくれる人に尽きますね。入口でもその要素は必要なんですけど、育成して独り立ちして仕事していく中でも、ずっとそこに基づいたアドバイスを伝え続けていくことになるので。
⎯
これまで多くの社員を採用、育成してきて印象的な出来事ってありましたか?
 松村
松村ひとりひとりについていろいろ出来事はありますけど…。そうですね、20代半ばで入社してくれたメンバーが、もう6〜7年経っているんですけど、今は一人前にチームを率いていて、今度は「ソニックガーデン流」を伝える立場になってる。これはちょっと嬉しいかな。
僕が上手に伝えられたのか、もともと彼に素養があったのかはわからないんですけど(笑)。
僕が上手に伝えられたのか、もともと彼に素養があったのかはわからないんですけど(笑)。
⎯
単にその方がソニックガーデンにマッチしていたのだとしても、そこを見抜いて引っ張ってこれたということじゃないですか。
 松村
松村そうですね、ありがとうございます。
でも本当にみんなそれぞれ活躍しているので、ソニックガーデンに来て良かったなと思ってくれている人たちは多いのかもしれないですね。
でも、結果ソニックガーデンを辞めることになった、入社できなかった、というのが失敗かと言うとそうとも言い切れないですし。
でも本当にみんなそれぞれ活躍しているので、ソニックガーデンに来て良かったなと思ってくれている人たちは多いのかもしれないですね。
でも、結果ソニックガーデンを辞めることになった、入社できなかった、というのが失敗かと言うとそうとも言い切れないですし。
⎯
そうですね、「ここじゃない」ということがわかったということですもんね。
 松村
松村
育成とか教育において、成功も失敗も定義できないなと、つくづく感じています。
「ソニックガーデン流」をどう伝えるか
⎯
育成の過程におけるコミュニケーションは、対話が中心ですか?
 松村
松村
基本的には対話です。対話が多いので、カレンダーが埋まりがち。
⎯
いつも誰かと対話している状態になるんですね。話し合うしかない。そこにチートはないですよね。

 松村
松村効率を考えれば、チートしたいですけどね。倉貫さんみたいに、ブログやラジオで、ある程度の自分のロジックを形にしてアウトプットするってことができるのもいいなと思うんですが、僕はそういうことがあまり得意じゃないんです。どちらかと言うと、相手のフィードバックがあって、そこからアドリブで一緒に考えていくのが得意ですね。
⎯
ひとりひとりの面倒を見る方法って、結局そういうことになりますよね。
 松村
松村そうですね、まずそれぞれの考えてることを聞かないと始まらない。でも僕、結構喋っちゃうタイプで、いつも「喋りすぎたな」って思うんですよね。「もっと聞けばよかったな」って(笑)。
何か具体的な出来事があった時に、「こうするとソニックガーデン的になるね」って話をすることが多いかな。
何か具体的な出来事があった時に、「こうするとソニックガーデン的になるね」って話をすることが多いかな。
⎯
「ソニックガーデンの価値観」という軸に対して、「今どこに向かってるかな」とアプローチするんですね。
 松村
松村特に入社直後とか、ソニックガーデンにいる期間がまだ短い時はそういうことをよく伝えてますね。みんな価値観についてよく知ってはいるんですよ。でも実際それを実行するには、自分がやったことや経験したことの中からアプローチの方法を伝えるのが1番しっくりくるし、学びとして深いので、対話を通して伝えることになりますね。
⎯
人と話すことが多いお仕事ですね。対話はそれほど苦にならない性格ですか?
 松村
松村ふりかえりは得意だし、そのフォーマットでやるのは慣れてるので大丈夫です。でもテーマが何もない中で喋るのは得意じゃないですね。
「フリーテーマで」なんて言われたら基本喋らなくなります(笑)。あと、人数が5人ぐらいの集まりになってくると、これも僕は基本的に喋らない。サボります。
「フリーテーマで」なんて言われたら基本喋らなくなります(笑)。あと、人数が5人ぐらいの集まりになってくると、これも僕は基本的に喋らない。サボります。
⎯
聞いてるからみんな喋っといてー、みたいな感じですか(笑)?
 松村
松村僕、基本的にサボりたい人なので。プログラミング自体もサボるために自動化するじゃないですか。
⎯
合理的ですね。
 松村
松村最近は経営チームメンバーが全社員と1on1をやるんです。それもね、「一応こういうことを聞けたらいいね」ぐらいの指針はあるんですけど、割とフリーテーマなんですよ。
⎯
「最近どう?」みたいなものですよね。大変、苦手じゃないですか。
 松村
松村そうなんですよ。結局「困ってることある?」みたいなスタンスで、ずっと仕事の話をしてたんですね。でも他のメンバーに聞くと、もっとプライベートに突っ込んでたり、将来について話してたりして。僕は基本的に「今困ってること」「今の仕事の話」みたなのばっかりで、「あれ、これでいいんだっけ?」って(笑)。
⎯
他人のバックグラウンドに言及するのって、ちょっと怖いですよね。自分が聞かれたくないタイプだったりするとなおさら。
 松村
松村そうですね、僕自身も自分の話を、自分からするのが苦手。聞かれれば普通に話しますけど。だから話題にする発想がそもそもないのかもしれないですね。今の仕事における問題解決を先にしたいと思ってしまう。
⎯
それが役割でもありますしね。さっきも言いましたけど、合理的ですね。
 松村
松村
究極に合理的だと思います。自分のタイプとしては。
自分は自分、他人は他人
⎯
働くにあたって、自分の中に決めごとって何かありますか?
 松村
松村ないです。というか、「こだわらない」のがこだわりですね。「決めつけない」が逆に信条かもしれない。
ちょっと抽象的になりますけど、仕事していく上で、何事も多面的に見ることが大事だと思っています。ひとつのことにこだわりすぎないように、あえてしているかんじですね。例えばディスカッションしてて、「こういう方向性で、こうじゃない?」とまとまった時に、「いやほんとか?いいのか?」って一度は考えます。
ちょっと抽象的になりますけど、仕事していく上で、何事も多面的に見ることが大事だと思っています。ひとつのことにこだわりすぎないように、あえてしているかんじですね。例えばディスカッションしてて、「こういう方向性で、こうじゃない?」とまとまった時に、「いやほんとか?いいのか?」って一度は考えます。
⎯
1回立ち止まって考えるんですね。
 松村
松村うん、よく立ち止まります。立ち止まって、「こちら側の視点から見たらどうだろう」っていうのを頭の中でよくやっています。「クリティカルシンキング」というんですね。批判的思考。
⎯
でも、全員で盛り上がって、ある種狂乱状態みたいになっている時に、1人そういう人がいないと、後日えらいことになったりしますよね。議事録を読み返したら全然だめだった、みたいな…。
 松村
松村そうそう。そこでノリが悪いってことになるかもしれないんですけど(笑)。俯瞰的に見てものを考えるようには、自然となってますね。

⎯
たくさんの人を見るお仕事だと、そういう視点が必要なんですね。自分と全然考え方の違う人もいるし、ゴールを設定してあげても、辿るルートがまったく想定外だったりということもあるでしょうし。
 松村
松村教育していても、「僕だったらこうする」ことが、相手の目線で考えたら、僕とは違う思いがまずあって、受け取り方も当然違う。だからそれをある程度汲んでから「僕だったらこうするよ」と伝えるかんじになりますね。
⎯
それほど人を見ていると、ちょっと話したらタイプがわかるとか、つい分析してしまうとか、ありそうですけども。
 松村
松村ストレングスファインダー(米国ギャラップ社の開発したオンライン才能診断ツール。個々の長所を知ることができる)をソニックガーデンではよく使うんですけど、「個別化」という要素が入っていますね。確かに、個々人の強みを把握するのが得意で、どうアプローチしてあげるのが良いか、というのは常日頃考えている気がしますね。あと、年賀状はひとりひとりに違うメッセージを書かないと気が済まない(笑)。
⎯
自他の区別がはっきりしているんですね。自分と他人が全然違うんだとわかってる、境界線をちゃんと引いている人だからこそ、ひとりひとりをきちんと見ることができるんじゃないでしょうか。
 松村
松村境界線がある方なんだなという気はします。昔から母親に「よそはよそ、うちはうちや」ってずっと言われていたので…。あれで「ああ、外と内があるんだな」と認識したのが最初かもしれない。
⎯
原体験ですね、それは。よく聞く非常にシンプルな言葉ですが、大事な真理が詰まっているのかもしれない。「人を育てる」ためには必要な能力だと思います。
 松村
松村そうですね。この人はこの人だ、僕とは違うと思うことは大事です。一方で共感してあげることも本当は大事だと思うんですけど、僕はそこがあんまり得意じゃないので、その分ちゃんと相手を分析して、強みを発揮するにはどうするか、認識をより良くするにはどうするかっていうのは、より考えてあげるようにしています。
「個」を育て、「個」が集まって「組織」になる
⎯
今、特にお仕事で取り組んでいることって何かありますか?
 松村
松村最近、ソニックガーデン全体として、チームビルディングに取り組んでいるんです。組織論から勉強して。これまでの、普通のヒエラルキーがある組織構造じゃなくて、もっとアメーバ的な、個々人が判断して動く感じに。これからの、変化の大きい時代は以前のような構造だと対応しきれないので。
⎯
じゃあ「個」を育てるところから、その新しい組織をビルドするところまで繋げるんですね。
 松村
松村そうですね、個が新しい組織構造のための視点を持てるように育成していくっていうかんじですね。そのために、組織を作るというところもやっていかんといかんなあと。
⎯
「個」が集まって組織になるわけだから、全体を見て整えるのも仕事のうちになりますね。
 松村
松村結局そうなりますね。
ずっと育成の過程で伝えているのは「視点を増やせ」ということです。中途から入った人は特に、前職で「自分」という視点だけを持って働いていたという方が多いんです。
例えば、「上司からこう言われた」「だからやる」ぐらいの範囲でしか考えていない。考えて欲しいのは、「上司はどういう気持ちでそれを言ってるんだ」というところ。さらに言えば「その上の、社長はどう考えてるんだ」というところまで含めて物事を考えないと、最大のパフォーマンスは出ない。
ずっと育成の過程で伝えているのは「視点を増やせ」ということです。中途から入った人は特に、前職で「自分」という視点だけを持って働いていたという方が多いんです。
例えば、「上司からこう言われた」「だからやる」ぐらいの範囲でしか考えていない。考えて欲しいのは、「上司はどういう気持ちでそれを言ってるんだ」というところ。さらに言えば「その上の、社長はどう考えてるんだ」というところまで含めて物事を考えないと、最大のパフォーマンスは出ない。
⎯
確かにそこには「そう言われた自分」しかいないですね。「なんで?」がない。
 松村
松村これをソニックガーデンの仕事で言うと、「お客さん目線はどうなの?」だったり「システムを使うユーザー目線どうなの?」というのを総合的に考えるようになってね、ということですね。
これからはさらに次のステップに進みたくて、組織の中、ソニックガーデンの中でのいろんな視点を持ちたいと思っているんです。倉貫さんの視点かもしれないし、同じチームの人間の視点かもしれない。そういうたくさんの視点を持ってみんなが行動できるようになるといいなあと。
これからはさらに次のステップに進みたくて、組織の中、ソニックガーデンの中でのいろんな視点を持ちたいと思っているんです。倉貫さんの視点かもしれないし、同じチームの人間の視点かもしれない。そういうたくさんの視点を持ってみんなが行動できるようになるといいなあと。
⎯
外側にも内側にも視点を増やしていくと。
 松村
松村以前に読んだ本に、良い組織、成長する組織は、メンバーがお互いに成長することに対して興味を持っている。フィードバックしあったり、なんでも言い合える環境が成長を促すし、組織としても広がっていく、というようなことが書いてあって、確かにそうだなと。
今のメンバーでもその要素はちゃんとありますけど、どうしても社歴が長いメンバーの方がお互いに言いやすい。後輩が僕にフィードバックしてくれるってことはあんまりないんですよね。そこが本当に「みんなで」になったらもっと面白いよなと思います。
今のメンバーでもその要素はちゃんとありますけど、どうしても社歴が長いメンバーの方がお互いに言いやすい。後輩が僕にフィードバックしてくれるってことはあんまりないんですよね。そこが本当に「みんなで」になったらもっと面白いよなと思います。
⎯
そうですね、本当にフラットに。経験を積んでいても失敗しますし、間違うことだってありますし。
 松村
松村僕も適当な人間なのでミスするんですよ。そういう時は指摘してもらいたい。まあ、僕が「ミスしてませんよ」みたいな顔するから悪いのかもしれないんですけど(笑)。
⎯
みんなで何でも言い合える場になったら、絶対に面白くなりますね。
 松村
松村そうです。今の50人でもっと忌憚なく言えるようになって、僕もフィードバックをたくさんもらったら、もっと成長して、組織として伸びていける気がします。「成長したい!」って熱く思っているわけじゃなくて、こう、ただただそれは楽しそうだなーって思います。
⎯
そこも伝えていくということですね。この場をもっと面白くするためにはこういう方向だよと。ソニックガーデンを楽しくするために。
 松村
松村そうですね、よりみんなが楽しくなっていると面白いし、僕も面白さが高まっていくし。
まだまだ進化の最中にいる

⎯
人数が増えてきて、これからも少しずつ増えるわけで、育成の仕事をお一人で続けるのは大変ですね。
 松村
松村最初の方でちょっと触れましたが、最近は育成もチームにして、僕は直接育成する人のメンターのような立場になりつつあります。そこも含めてチームとしてどう動くかをまた考えないといけないフェーズにきました。教育するための、超メタ視点のフィードバックを考えるっていう。
⎯
やっぱりまだまだ真っ只中ですね、進化と歴史の。
 松村
松村新しく問い合わせてきてくれるお客さんもいますし、現在僕らが提供しているお客さん自体も成長して、もっとやりたいという要望が多いんです。そこに応えたい。
提供するためにいいエンジニアを増やして、提供できる形を作っていくと、みんなハッピーになるんだろうなと思います。ちゃんと真摯に仕事をしているとそうなるのかな。
提供するためにいいエンジニアを増やして、提供できる形を作っていくと、みんなハッピーになるんだろうなと思います。ちゃんと真摯に仕事をしているとそうなるのかな。
⎯
楽しくするためにどうするか考える。そのブレない姿勢の先に組織としての成長があって、みんなのハッピーに繋がるんですね。
この先もずっと続くソニックガーデン、どうなっていくのか楽しみです。今日はどうもありがとうございました!
この先もずっと続くソニックガーデン、どうなっていくのか楽しみです。今日はどうもありがとうございました!
取材/文 土佐光見