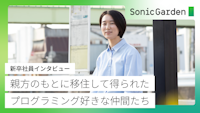探せボトルネック!確かな分析力で組織を「いい感じ」に整える

今回登場するのは、ソニックガーデン創業メンバーの安達 輝雄(あだち てるお)さんです。
たった5人から始まったソニックガーデン。徐々に社員が増え、案件が増え、刻々と組織が姿を変えていく中、常にチームを「いい感じ」に整える役割を担ってきました。
その稀有な視点の源泉は何か、チームを整えるために必要なことについて、そして自己分析や、仕事と未来への思いまで、たっぷりお聞きしました!
目次
いつも「いい感じ」に整えるのが仕事
⎯
では、自己紹介をお願いします。
 安達
安達安達 輝雄(あだち てるお)です。現在はCIO(取締役執行役員)です。主に「納品のない受託開発」に関わっていますが、開発自体のウェイトは小さくて、マネジメントがメインです。開発チームやデザイナーチームをまとめて、いい感じにするという仕事ですね。あとは、サービスの企画や設計にもぐいぐい入っていって、プロジェクト全体を見る、ということもやっています。
⎯
「チームをいい感じにする屋さん」という認識で合ってますか?
 安達
安達そうです(笑)。
⎯
全部がわかっていないとできないお仕事ですね。開発のことはもちろん、対外的なことも。
 安達
安達そうですね、開発経験がないが故に、開発者たちと気持ちがズレてうまくいかなくなってしまうマネージャーというのは、一般的によく聞く話です。僕はエンジニア上がりなので、経験を踏まえてメンバーの気持ちや状況を理解しつつ、全体をいい感じに動かしていくように意識しています。
⎯
安達さんはソニックガーデンの創業メンバーですが、当時から全体を見ていい感じに整備するような役割が多かったんですか?
 安達
安達創業当時は5人とかなり人数が少なかったので、みんなで協力してやってましたね。アプリケーション開発だけでなく、システムの運用とかシステム構築もやってたので、細かいことにこだわりすぎず、共通化しつつ、運用やインフラ構築のコストを減らして、当時からなるべくアプリケーション開発に注力できる環境を目指していました。
どんどんメンバーが増えて、案件の数も増えて、インフラのバリエーションも増えてきたあたりで、見ないといけない観点が激増して、急に手が回らない状況になったんですよね。その時にアプリケーション開発を軸に置きながらインフラを得意とする者が集まって、なんとかいい感じになっていった。
どんどんメンバーが増えて、案件の数も増えて、インフラのバリエーションも増えてきたあたりで、見ないといけない観点が激増して、急に手が回らない状況になったんですよね。その時にアプリケーション開発を軸に置きながらインフラを得意とする者が集まって、なんとかいい感じになっていった。

⎯
今ある委員会(※1)の軸もそのときにできたんですね。
 安達
安達そのときぐらいにできましたね。本当に案件の数が増えてきて、セキュリティを会社全体として見ないと、というところで委員会が生まれました。そうなってくると今度は情報システム部みたいなものも必要になってくるな、と考えてスタンド委員会(※2)ができて…そんな感じでいろんな委員会が立ち上がった。
※1…ソニックガーデンでは、セキュリティやプライバシー保護、品質管理、労務マネジメントなど、企業を健全に継続させるために必要な仕事を「委員会活動」と呼び、全員で分担して取り組んでいます。
※2 …情報システム委員会の通称。
⎯
そんな数々の委員会をまとめたり全体を見渡したりするのも、現在の安達さんの役割のひとつなんですよね。
 安達
安達そうです。委員会が立ち上がった当時は、自分が手を動かしたりしてたんですけど、そこから徐々に視野を上げていって、今はまとめ役というか、それぞれの委員会のパイプ役というポジションですね。
⎯
一度に見えるものが多いタイプなんですね。草食動物のような広い視野をお持ちです。
 安達
安達徐々に広がっていったと思っていますけどね。求められるものが増えた結果というか。
⎯
求められたからできるというものでもない気がしますが…。求められて初めて意識してなかった能力が開花した感じですか?
 安達
安達
自分が嫌だと思ってることでは、視野って広がらないと思うんです。でも興味のあることだったら、自然に広げることができるんじゃないかな。インフラとかセキュリティとか、個人的に興味があった。だから自然と広げていくことができたと思っています。
目標志向・分析思考・最上志向
⎯
ちなみに興味ないことってありますか? 「これはできない」という仕事。
 安達
安達営業は苦手ですねえ。喋りが得意じゃないんですよ。相談されて答えることはできるけど、自分から売り込むっていうのは全然できない。それをやれって言われてもだめ。多分すぐに諦めると思います。
⎯
今のポジションは、ごく自然に選んだ仕事というか、必要かつ興味があったから目について、吸い寄せられてついた役割だったのかもしれませんね。
 安達
安達僕、ストレングスファインダーでは「計画性」みたいなところが強いんですよ。最上志向かつ目標志向。その次に分析思考っていうのがあったかな。僕は基本的に、目に見えない、自分の中でイメージできない目標に向かって走れるタイプではないんです。どちらかというと目標のためにフェーズを区切って、まずこの最初の部分だけを集中的にやろう、そのためにはこういうことが必要だよね、と逆算方式で考えるのが得意。
⎯
なるほど、足場を組み立てることが得意。どうやって登っていくかを分析するんですね。
 安達
安達そうです、そこはすごく考えますね。
⎯
目標志向と分析思考ですね。最上志向というのは、現状で一番よくしようということですか?
 安達
安達それもあるし、自分の弱みには目をつむって、強みを生かすよう注力するというところもあるみたいですね。
確かに僕は不得意なことは基本的にやらないんですよ。そこで戦うことはせずに、自分が一番輝ける場所をすごく意識する。例えば、ソニックガーデンの中でもRubyでの開発を強みとしている人がたくさんいるんです。だから同じフィールドで戦ってても自分はもう輝けない。すでにすごいエンジニアがたくさんいるんだから、フィールドを変えることを考えるんです。そんなわけで今はチームビルディングですね。それを得意としてる人が少ないからそっちで存在感を出す。インフラもそうです。得意な人が少ないからそれを極めて、なおかつ自分も楽しい。そんな感じで力を発揮できる場所を探して仕事しています。
確かに僕は不得意なことは基本的にやらないんですよ。そこで戦うことはせずに、自分が一番輝ける場所をすごく意識する。例えば、ソニックガーデンの中でもRubyでの開発を強みとしている人がたくさんいるんです。だから同じフィールドで戦ってても自分はもう輝けない。すでにすごいエンジニアがたくさんいるんだから、フィールドを変えることを考えるんです。そんなわけで今はチームビルディングですね。それを得意としてる人が少ないからそっちで存在感を出す。インフラもそうです。得意な人が少ないからそれを極めて、なおかつ自分も楽しい。そんな感じで力を発揮できる場所を探して仕事しています。

⎯
おお、チームビルディング。楽しいですか?
 安達
安達楽しいですね。チームビルディングって面倒臭いイメージがあるじゃないですか。人と人との関係性を考えるとか…。
⎯
難しそうに思われますよね。
 安達
安達人をコントロールしようとすると難しいんですけど、人間自体じゃなくて、人が集まってる中で、うまくいってないところを見つけて解消する、と考えるんです。人を見ずに状態を見る。そこのボトルネックを解消していけば、自然とチームは良くなる。
⎯
すごい! それは学んで得たものですか? それとももともと持っていた感覚なんですか?
 安達
安達研修を受けてわかったというのもそうなんですけど、納品のない受託開発というもの自体がそもそも、課題は何なのか、それをどう解決していくのかというところにポイントを絞ってサービスを良くしようという考え方なんですよ。「課題は何なのか」というところをすごく深掘りするんですよね。だからその延長線上で、人というよりチーム、そのボトルネックという課題があるから、それを解消すればいいだけだよね、という捉え方をしています。
⎯
なるほど、チームもそうですけど、納品のない受託開発自体に、実はチームビルディングが深く関わっているんですね。
 安達
安達そうです。最初のうちは関係者が少ないからそこが問題になりにくいだけだったんじゃないのかな。
ソニックガーデンは5人という小さな集団から始まったじゃないですか。そこから徐々に人数が増えていったんですが、実はそのときにもいろんな問題があって、常に倉貫さんがそのボトルネックを解消しようとしていたんですよね。そのあたりを見てるから、案件単位でのチームが大きくなる今、そのときの学びを生かしながらやってるだけかもしれないですね。
ソニックガーデンは5人という小さな集団から始まったじゃないですか。そこから徐々に人数が増えていったんですが、実はそのときにもいろんな問題があって、常に倉貫さんがそのボトルネックを解消しようとしていたんですよね。そのあたりを見てるから、案件単位でのチームが大きくなる今、そのときの学びを生かしながらやってるだけかもしれないですね。
⎯
学びを生かしつつ、現在ソニックガーデン全体を最適化させる役割に積極的にあたっていると。
 安達
安達それを率先してやる立場にありました。これがまた最近ひとつ違うステージに移行していて、より範囲を分割して、全体の関係性をフラットにしようと取り組んでいるんです。今までは僕とか一部のメンバーが考えないといけなかった最適化を、もっとみんなで考えようというスタンスですね。
⎯
いつも全員が当事者であろうという。今社員は50人くらいでしたっけ?
 安達
安達そのくらいですね。マネージャー層がなんとかしてしまうと、どうしても現場と乖離してしまうんですよね。尻拭いをするのがマネージャー層、みたいになるのはやっぱり良くない。結局お互いにストレス溜まってしまうので、みんなで考えるってところにシフトしています。
徹底的に言語化する。空気は読まない。

⎯
何でも口に出すタイプですか?
 安達
安達僕はずけずけ言うタイプですね。お客さんにも言います、空気読まずに(笑)。でも言わないと伝わらないし、みんなも考えるきっかけにならない。だから言うということは意識してますね。
あと、独立前に倉貫さんからOJTなんかもしてもらっていた頃、とにかく何を言っても「で?」って聞き返されてたんですよ。この経験も生きてますね。
あと、独立前に倉貫さんからOJTなんかもしてもらっていた頃、とにかく何を言っても「で?」って聞き返されてたんですよ。この経験も生きてますね。
⎯
言葉にして全部出すことを求められたと。
 安達
安達「で?」っていう言葉には後ろがないじゃないですか。自分なりに考えてくれってことですよね。何を考えてるのか全部言ってくれよっていうスタンスだから。あれには鍛えられました。
⎯
徹底的に言語化する訓練を知らず知らず受けていたということかもしれませんね。
好奇心は常に旺盛に。「わかってないこと」には口出ししない。
⎯
最初にTISの社内ベンチャーから始まったソニックガーデンですが、いざ独立すると言われたときは、特に躊躇するところもなく参加したんですか?
 安達
安達全然躊躇はなかったです。技術的にも面白そうだし、そのとき独身で身軽だったということもあって、やってみよう!っていう感じで。悩む時間もほとんどなかったと思います。倉貫さんに「独立しようと思ってるんだ」って言われたときも「いっすね」って一言返事して、「軽っ!」って言われたのを覚えています(笑)。
⎯
軽い(笑)。社会人のスタートからずっとエンジニアなんですか?
 安達
安達そうですね、いわゆるインフラエンジニアと呼ばれる役割でした。サーバーを見たりとか、実際にデータセンターで作業したりとかしてましたね。最初のうちはそこだったんですけど、OJTとかいろいろやるうちに、自然とサービスに関わる全部を知りたいなという気持ちが出てきて、インフラから抜けてアプリ開発もするし、プロダクトオーナーみたいなことも、営業的なこともやりました。ユーザーサポートもやったし…。
⎯
ユーザーサポートまで? いろいろ経験されたんですねえ。
 安達
安達そうなんですよね。だけどそういう経験があるから、お客さんが何が言いたいんだろうと考えるようになったのかもしれません。
⎯
独立のエピソードからもそうですが、好奇心が強いんですね。ひとつを知ると全体を知りたくなるというところも。
 安達
安達はい、強いですね。見えてないところやわかってないところって、口出ししても外から知らない人が言ってるだけ、みたいになるじゃないですか。そういうことは僕自身もやられたらすごく嫌だと思うんです。だから外から見ただけでなんか言うよりは、中に入ってある程度理解して、それから言いたい。
⎯
わからないことは言いたくないですよね。非常にシンプルだし、行動力もあるなあと思います。
 安達
安達僕はあまり頭が良くないというか、記憶機能が優秀でないので、if文をたくさんつなげて考えるのが好きじゃないんです。「無理!」ってなっちゃう。だからなるべく条件分岐をなくしてシンプルにして、自分の頭で理解できるようにするというのはありますね。
シンプルにすれば問題も課題もよく見渡せる
⎯
逆に言うと、目標に一番効率よく到達する筋を考えるのが上手ということですね。シンプルさは仕事するときにかなり意識するところなんですか?
 安達
安達そうですね。とにかくシンプルじゃないと自分ができないから(笑)。仕事って、課題やゴールがあって、その解消を目指すものじゃないですか。その解消範囲を極端に広げすぎないことも意識してますね。
最終的なゴールをいきなり目指すのではなく、細かくフェーズを作ってそれをひとつずつ頑張る。まずはフェーズ1、それが終わったらフェーズ2、というふうに考えます。問題を大きくしすぎない。
最終的なゴールをいきなり目指すのではなく、細かくフェーズを作ってそれをひとつずつ頑張る。まずはフェーズ1、それが終わったらフェーズ2、というふうに考えます。問題を大きくしすぎない。
⎯
これぐらいの階段を設置すれば、目標にはこれぐらいの労力で到達できるだろうと考える。「できそう」にするんですね。
 安達
安達
あんまり遠い目標にしすぎると、みんな何をやっていいかもわかんなくなりますよね。そのうち目的もわかんなくなっちゃって、最終的にばらばらになる危険性もあります。そこを自分の中で整理するためにも細分化して考えると、全体としてもちゃんと動く。
⎯
そうですね、たくさんの人を動かさなきゃならないし、みんなにわかってもらわなきゃいけない。
 安達
安達そうそう。すごく大変。だからこそ目標を分割していくところはすごく意識しています。
⎯
それは同時にメンバーが今どれだけできるのか、ということも把握しなきゃいけないじゃないですか。メンバーによってだいぶ変わりますよね?
 安達
安達うーん、でも状況はコントロールできないから、そのときそのときで、ボトルネックを見つけてそこを解消していけば良いと考えてますね。あんまり最初に先入観があると、考える範囲も狭まってしまうから。それは毎度全体を見て判断しますね。
⎯
ボトルネック探しが得意という能力がそこで発揮されるんですね。
 安達
安達そうだ、そっちの方かもしれないですね。昔から障害が発生すると、首を突っ込んで一緒に分析したり問題を探し出したりしていたんですね。もちろんフォローなんですけど、自分の興味で間違い探しをしたかった。

⎯
問題のさなかにいる人は、どこにバグがあるのか見えづらくなりがちです。そこへぽんと入ってきて、間違い探しを一生懸命してくれる人っていうのは、組織には必要だと思います。
 安達
安達そう言ってもらえると嬉しいです。僕は割と疑り深いというか、事実と仮説をきっちり切り離して考えたいタイプなんです。例えば納品のない受託開発でサービスの規模を拡大するときにも、この機能を追加したらこの数値が伸びるよね、伸びなかったとしたら何かが間違ってるんだよね、そのときは機能を見直しましょう、って仮説を立てて、事実を確認してというサイクルを常に繰り返します。そこにボトルネックがあるならそれは何かを見極める。そもそも感覚に頼ることは少ないんです。まったくないわけじゃないんですけど。
⎯
そうするとどの高さの階段を設置して、どうやって登っていけばいいのかが見えてくるんですね。それは圧倒的分析力ですね。そこについ幻想や希望的観測を乗せてしまう人は多いと思います。
 安達
安達でもこれも反転するとだめな能力でもあって、新規ビジネスを立ち上げるときには僕はあまりうまく振る舞えないと思います。
⎯
夢が見られないから?
 安達
安達そう、夢が大事なときってあるじゃないですか。そこに現実を持ってくるのは意味がない。現実は今の状態であって、夢とはちょっと違う考え方が必要で、そういうところは向いてないんだろうなって自分でも思います。
⎯
じゃあ夢がある人のそばで、そこに行くための具体策を考えるのが良いポジションなのかもしれないですね。船長が宝物を目指すとき、航路を見極めてあげる、みたいな。
 安達
安達ああそうですね。どうやったらそっちへ行けるのかなって見ようとする。目標志向ですね。
ひとつの成果は横に展開してさらに生かしたい
⎯
これからやりたいこと、進みたい道などありますか?
 安達
安達納品のない受託開発を十数年やってきて、当初から関わっているお客様のビジネスがどんどんスケールしていってるんです。そういうお客様に合わせて道を切り開いていってるところなんですが、それをより多くの他のお客様にも展開できるように、ソニックガーデンのサービスプランにしていきたいと思っています。
⎯
切り開いた方法を横展開したいということですね。
 安達
安達そのお客様だけ、ひとつのケースだけうまくいった!じゃもったいないですから。横に展開して、ちゃんと他でも価値がある状態にすることが本当の成果かなと考えています。
⎯
もったいない、確かに。より多くの人にフィットする仕組みにできたらメリットですもんね。
 安達
安達成果を大きくしたいというのが自分の中にあるんでしょうね。
⎯
大きくしたいというよりは便利にしたいんじゃないですか? 自分が得た成果が大きいんだぞ!というよりは、みんな!便利だよ!みたいな。
 安達
安達そうですね、より多くの人をより便利にしたい、助けたいって思います。還元したい。「これやったよ、すごいだろ」って威張りたいわけじゃないんです。どちらかというと裏方でいい。目立たなくてもいいから、より多くの人がハッピーになるようにしたいですね。
あ、自分が構築したものがうまくあてはまってる。くふふ、って裏で思う感じです。どうだ、うまくいっただろう?めちゃくちゃ便利だろ?って(笑)。
あ、自分が構築したものがうまくあてはまってる。くふふ、って裏で思う感じです。どうだ、うまくいっただろう?めちゃくちゃ便利だろ?って(笑)。
目で見た事実を蓄積して、「いい感じ」を作り続ける

⎯
ご自身についてはどうですか?
 安達
安達お客様が今後もどんどん成長してサービスを拡大していく中で、今は自分なりのやり方で最善を見つけるようにしていますが、もうちょっと外部の視点を入れたいなと思っています。ソニックガーデンよりももっと大規模な組織とか、そういうところの知見を勉強して貯めて、また社内に持ち帰って反映したいですね。
知見を広げるために、実は割と、納品のない受託開発で携わったシステムを使っているユーザーのところに直接行ったりもしてるんですよ。実際に操作しているところを見たり、気持ちを教えてもらったりして、それを持ち帰って実装するという活動もしていて。今後もそれは続けていきたいです。
知見を広げるために、実は割と、納品のない受託開発で携わったシステムを使っているユーザーのところに直接行ったりもしてるんですよ。実際に操作しているところを見たり、気持ちを教えてもらったりして、それを持ち帰って実装するという活動もしていて。今後もそれは続けていきたいです。
⎯
外で見識を集めてきて、それを最終的に形にしてるんですね。自分の中にある理論だけを使うんじゃなくて。
 安達
安達人から聞いた話を鵜呑みにできない質なので。自分の目で見て触れて、どちらかといえばそっちなんです。想像でいろいろするタイプではない。
⎯
まずは事実を確認したい、という気質がここにも役立ってる! そうやって視野を広げるともっとすごいことができるかもしれないですもんね。もっと便利になるかもしれないし。
 安達
安達結局、とにかく視野を広げたいってことですね。僕は研究者タイプではないので、深く掘るというよりは、中ぐらいまで掘って広く知りたい。
あと、今はチームビルディングとか橋渡しの役割が多いんですが、このあたりが整って余裕が出てきたら、また開発にも注力したいですね。
あと、今はチームビルディングとか橋渡しの役割が多いんですが、このあたりが整って余裕が出てきたら、また開発にも注力したいですね。
⎯
やっぱり開発もお好きなんですね。
 安達
安達好きですね。だから、プログラミングでサービスを形にしていくっていうのは今後もやっていきたいです。マネジメントもするかもしれないけど、プログラマでもあり続けたいです。
⎯
ずっとものを作ることは忘れたくない。素敵ですね、そうやって整えて、永く「いい感じ」でいられますように。本日はありがとうございました!
取材/文 土佐光見